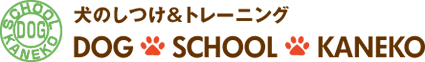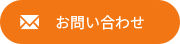こんにちは。ドッグスクールKANEKOです。
相談を受けたり、カウンセリングをしたり、ご提案をしたり、トレーニングをしたりしていると、ご家族から「可哀想」という言葉をよく耳にします。
愛犬の様子や色んな場面をみて「可哀想」と思う事はあるかもしれませんが、愛犬との長い生活の中で「愛犬が可哀想」にならないためにはどうしたらいいのか、考えるきっかけのひとつにしていただければと思います。
はじめに
愛犬にしつけをしたり、トレーニングをしたりすると、愛犬が嫌がる場面があると思いますが、その様子をみて「可哀想」としつけなど「本来やりたかった事」を断念する方がいます。
愛犬が嫌がる事に対して、“愛犬が嫌がる”から「可哀想」と避ける(やらない)のか、愛犬が嫌がっても“必要な事”だから「愛犬のために」やり続け「嫌がらない」ようにしていくのか、愛犬との関わり方でその後の生活の分岐点になりやすいです。
「可哀想」の種類
ご家族が「愛犬が可哀想」と思いやすい場面は細かくわけるとたくさんあるので、「可哀想」の種類を大きく分類してみようと思います。
一時的な「可哀想」
しつけやトレーニングをする上で、「その場」や「一時的」に「可哀想」になりやすい事の一例を書いてみます。
愛犬が“変化”を受け入れるまでの「一時的」な反応なので、「継続的に繰り返し」練習をしていくと、愛犬が「何をしたらいいのか」を学習(理解)し、習慣になったり、受け入れられるようになったりする事が多いです。
愛犬が嫌がる事をする
愛犬のしつけや手入れをする時に愛犬が嫌がる事があると思います。
しつけや手入れは愛犬にとって「必要な事」なので、“嫌がるからしない”ではなく“必要な事だから嫌がらないようにする”ようにご家族の意識を変えていただくと愛犬も「嫌な事」の受け入れ方を理解しやすくなります。
(しつけについて) 愛犬をしつけのしやすい仔に育てるコツは?
愛犬が「なにを嫌がっているか」をよくみて「嫌がっている事」は「愛犬にとって必要な事か不要な事か」をご家庭内でよく話し合ってみて下さい。
ただ、方法を間違えると「余計に嫌がる(悪化する)」「愛犬が怪我をする」「ご家族が怪我をする」可能性もあるため、しつけはトレーナー、お手入れはトリマー(グルーマー)に相談や依頼される事をおすすめします。
愛犬に我慢をさせる
「愛犬がやりたい事を望むままさせてあげる」事が「愛犬にとっていい事」のように考えている方がいますが、「我慢をした事がない」愛犬はありとあらゆるものを拒絶し、抵抗したり反発したりしやすい傾向があります。
“我慢”を経験する過程では愛犬が「自分の思い通りにしたい」「今まで通り自由がいい」と主張したり嫌がったりする場面がありますが、「我慢ができる」と愛犬自身も愛犬との生活も色んな場面で選択肢を増やす事ができます。
愛犬にストレスをかける
愛犬のお困りの行動に対するトレーニングについてお話ししていると「それってストレスがかかりますよね?」と「愛犬にストレスがかかる = 可哀想」と感じる方は一定数います。
愛犬にストレスを全くかけない生活をするとは、
・愛犬の望むまま生活をする
・愛犬に支配された生活をする
・愛犬を甘やかす
と変換できると思います。
愛犬が人と生活する上では、大なり小なりストレスはかかります。
なので、ストレスはかかる前提で「本来ストレスになりうる事」を「ストレスと感じないように慣らす」事が愛犬にもご家族にも必要だと思います。
愛犬を甘やかした結果、許容範囲が狭くなりストレスをより感じやすくなる傾向があります。
今までの生活環境を変える
愛犬にお困りの行動がある場合、「生活環境の見直し」をしていただく事があります。
(しつけについて) 愛犬のしつけ、大事なことってなに?
例えば、愛犬が自由に動き回れる「ルールのないケージレス(フリー)」で生活している愛犬は、ハウスの練習など今まで経験したことのない「制限」や「ルール」が加わると過剰に拒絶する事があります。
(ハウスについて) 愛犬はなんのためにハウスするの?
生活環境は愛犬のしつけの基本になるため、基本ができていないとその先(しつけやトレーニング)へ進めない(ステップアップできない)事もあります。
実際にお会いする方でもSNSなどでもフリーにこだわる方が多いですが、まずはハウス(クレート)に慣れる事、ルールを守る事、人に合わせた生活をする事など基本的な事を愛犬に教え、愛犬が「しつけの基本」を理解してから、徐々に各ご家庭の生活スタイルにカスタマイズしていく方がいいと思います。
はじめからフリーの生活で愛犬が「なんでもできる自由な生活」をさせて、「あれダメ!これダメ!」と制限やルールを追加するのではなく、はじめに必要な制限やルールを教え「制限の範囲内(ルールを守れる)なら好きにしていいよ」と“条件付き”のフリーなど各ご家庭の生活スタイルに変えていく方がスムーズで、愛犬にも「何をすればいいのか」がわかりやすいため、余計なストレスや負担をかけなくていいケースが多いです。
長期的、継続的な「可哀想」
愛犬が嫌がる事をしない、愛犬に我慢をさせないなど、愛犬にとって必要な事を「可哀想」でしなかった結果、どういう事が起こる可能性があるのか、一例を書いてみます。
触れない場所がある
“愛犬が嫌がる場所を触らない”と、愛犬の身体で触れない場所ができやすいですが、以前は触れた場所も嫌がるようになると触れる場所がどんどん減る可能性があります。
愛犬を触れないと、日常の手入れができなかったり、サロンに依頼できなかったり、必要な診察や検査をしてもらえなかったり、介護ができなかったりする可能性があります。
我慢ができない
“愛犬が嫌がる事は全てしない”と、愛犬は「嫌がれば止めてもらえる」「嫌な事は嫌がればいい」と学習しやすいため、嫌な事はどんどん拒絶し、嫌だと伝える手段も強くなりやすいです。
なんてことない単純な事も我慢できず、過剰な反応や反発をするため、愛犬に関わろうとする人が減ったり嫌がられたりする可能性があります。
関われない人がいる
愛犬の望むまま生活していると、愛犬の作る序列の下位の人や「愛犬の思い通りに動いてくれない人」に対しての反発や攻撃が強くなりやすいです。
病院やサロンなどは「愛犬の思い通りにしてくれない」診察、検査、処置、作業などがあるため、ご家族には見せない拒絶反応を強くみせる事があります。
過敏、神経質
ストレス耐性が無さすぎると、ありとあらゆるものにストレスを感じるようになりやすいです。
「ビビリ」と表現されるタイプには、性質的な仔もいますが、日常生活の積み重ねや経験から、過敏で神経質な仔、気が立ってる仔もいます。
(ビビリについて) 愛犬のビビリ、どうしたらいいの?
(愛犬のなぜ?) 愛犬が吠えるのはなぜ?
ストレス耐性が弱いと「いつもと違う事」の全てを受け入れられない仔が多く、ちょっとした変化で体調不良(下痢、嘔吐、食欲不振など)になったり、パニックになったりする事があります。
ご家庭内でご家族構成が変わる事もあれば、災害も増えている昨今では「常にいつも通り」ができない事もあり、愛犬には「過剰なストレス」がかかりやすい傾向があります。
できる事が減っていく
愛犬が「嫌だ」と拒絶した事を全て取り除いた生活をしていると、必要なお手入れやしつけも「嫌がる」と断念する事になるため、「愛犬が嫌がらない事」しかできなくなります。
現状維持ならまだいいですが、そういうケースは「嫌な事」がどんどん増える傾向が強いため、「以前は平気だった事」まで嫌がるようになり、結果として「できる事」がどんどん減ってしまう可能性があります。
選択肢が少ない
「できる事」が減ると、おのずと愛犬と一緒にできる事や愛犬との生活の選択肢が少なくなります。
例えば「愛犬が嫌がる」から「お留守番をさせない」生活をしていると、“いつでも”“どこでも”愛犬を一緒に連れていなかなければいけなくなります。
(分離不安について) 愛犬は大丈夫?分離不安ってなに?
「愛犬が嫌がる」から「ハウスをさせない」と、お留守番の間に色んなものを破壊したり誤飲したりせる可能性もあり、ハウスができないと預け先の選択肢が“ケージレスでお預かりできる”場所のみになります。
好意的に受け入れてもらえない事がある
愛犬が望むままの生活をしていると「自己中心的」になりやすいため、ずっと吠え続けていたり、すぐに噛んだり、マーキングをし続けたり、ケンカを売ったり買ったり、ご近所の方や愛犬と関わる方達から嫌がられたり、避けられたり、嫌われたりする可能性があります。
(叱る事について) 愛犬を叱っちゃダメなの?叱る事は可哀想?
愛犬と一緒に生活しているご家族は「いつもの事」と慣れてしまいがちですが、吠える声やお散歩のマナーなどは人それぞれ価値観があるので、ご家族が大丈夫な範囲でも周りの方々が同じように受け入れてくれるとは限りません。
愛犬もご家族も肩身の狭い生活をしなければならなくなるケースがあり、その時に「しつけをしよう!」と思ってもかなり大変な状態の事も多いです。
愛犬を「可哀想」にしないためには?
「愛犬に必要な事をしてあげる」事が大切だと思います。
「愛犬の望むままに生活する」のは一見理想的かもしれませんが、人と生活する上でのルールやマナーを教えてもらえない愛犬は、人間社会では嫌がられたり避けられたりしやすく、犬同士でもトラブルになりやすい傾向があります。
ドッグランを犬の社交の場にしている方もいると思いますが、自己中心的だと、愛犬自身はもちろん、愛犬と関わる他犬や他人にも負の経験(しない方がいい経験)や悪影響を与える可能性があります。
動物病院、トリミングサロン、ペットホテルなどを利用したくても「お断り」されたり、保定の人数を増やしてもらったり、鎮痛剤や麻酔を打たれたり、「+α」の処置や人員が必要になる可能性もあります。
さいごに
愛犬が嫌がる時に悲鳴をあげたり、「やめて」と噛もうとしたり噛んだりする事はありますが、愛犬が「嫌な事」を受け入れるために必要な過程でもあるため、一時的な「可哀想」を優先するのではなく、長期的に「可哀想」にならないために、愛犬に何をしてあげればいいのか考えるきっかけにしていただければ幸いです。
愛犬が悲鳴をあげるのがいい、噛みにくるのがいいのではないため、「痛めつけるのがいい」「愛犬が嫌がる事をすればいい」と勘違いされないようにお願いします。
何をどうすればいいのかわからない方は、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。