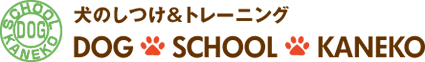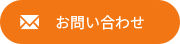こんにちは。ドッグスクールKANEKOです。
愛犬の仕草や態度について、ご家族が勘違いをして認識していたり、ご家族の都合のいいように解釈していたりする事により「愛犬のお困りの行動」が強化(悪化)するケースが散見されます。
はじめに
例えば、パニックになる程過度に興奮している愛犬を「愛犬が喜んでいる」「愛犬が楽しそう」と勘違いしているご家族がいます。
楽しいのも喜んでいるのも興奮のひとつですが、興奮の種類や度合いによっては微笑ましく見守っていい状態ではない事もあり、愛犬がどういう状態なのか把握せず(できず)「よくない経験」をさせてしまう事も多々あるように思います。
「愛犬の事はなんでもわかる」と自信があるご家族もいるかもしれませんが、客観的に愛犬について見直すきっかけにしていただければと思います。
愛犬は喜んでる?楽しそうにしてる?
愛犬が走りまわっていると「喜んでる」「楽しそう」と好意的に受けとる方がいますが、ご家族が制御不能なほど愛犬が興奮しているケースもあります。
(興奮ついて) 愛犬のその行動、本当に喜んでる?
愛犬が「楽しく」過ごす事は悪い事ではないですが、しつけ具合やご家族との関係性により、パニックになった愛犬の暴走を止められず、トラブルになったり(愛犬、ご家族、周りの人や犬が)怪我をしたりする可能性があります。
ご家族が「愛犬が楽しく過ごせるように」としている事(行動)が結果的に「よくない経験」をさせるだけのケースもあるため、基本的なしつけや愛犬との関係性が構築できていない段階では、制御不能になるまで「過度に興奮させる」事は控えた方が安心です。
尻尾を振っているのは嬉しいから?
愛犬が「尻尾を振っている = 楽しい、嬉しい、喜んでいる」と勘違いしている方は結構多い印象です。
ひとことで「尻尾を振っている」状態でも尻尾の位置や振り方で興奮、威嚇、緊張、警戒、萎縮など色んな意味があります。
上記のように尻尾の振り方だけでも愛犬の状態(サイン)を把握する事ができますが、ここを勘違いしていると、「遊んでいると思ったら他犬と喧嘩になった」などトラブルになる事があります。
お散歩は楽しいもの?
「犬を飼う = お散歩をする」という認識は犬を飼っていない方でもあると思いますが、どんな仔でも「お散歩が大好き」という訳ではありません。
お散歩も「事前準備」の有無により、楽しめずに義務感だけで過ごすご家族もいると思いますが、愛犬も性格や性質により「お散歩が苦手」な仔もいます。
(お散歩について) 愛犬のお散歩デビュー、準備はできてる?
お散歩が苦手な仔は、外の色んな刺激(ニオイや音)に過敏だったり、ビビリだったり、経験不足だったり、慎重だったり色んな理由があると思います。
慣れるまで「数をこなせばいい」場合もありますが、愛犬の性質や慣らす順番や方法によっては逆効果になり、どんどん外が苦手になり、ご家族との関係性に支障が出るケースもあります。
ご家族は「愛犬とお散歩に行きたい」かもしれませんが、愛犬の状態を確認して、事前準備をしたり、愛犬に合わせて無理のない範囲にしたりする事が必要だと思います。
吠えるのはビビってるから?
愛犬が吠えている時、「なぜ吠えているか」を勘違いしている方がいます。
(愛犬のなぜ) 愛犬が吠えるのはなぜ?
お散歩中に吠えるのは、吠えている対象にビビっているから、相手が好きだから、遊びたいから、恐怖心や警戒心からなど色々な理由があります。
吠えている行動を肯定的に受け止めるため「都合のいい言い訳」にしている方もいます。
吠える行動は他の方からは「騒音」にもなり得ます。
「○○だから吠えても仕方ない」ではなく、なぜ吠えるのか?なにに吠えるのか?愛犬の様子や状況を確認したり、吠えないためのしつけやトレーニングを検討されたりする事をおすすめします。
飛びつくのは嬉しいから?
「飛びつく行動」を「お困りの行動」として相談中に「嬉しくて飛びついちゃう」「○○が好きだから飛びついちゃう」というお話をお聞きする事があります。
(飛びつきについて) 愛犬が飛びつくのはどんな時?どうすればいいの?
愛犬が喜んでいれば、相手に好意を持っていれば「飛びついてもいい」と好意的に受け止めているご家族も少なくないです。
大型犬の場合は飛びつく事により相手が転んだら怪我をしたりするリスクがあるため、比較的「飛びつく行動」を「お困りの行動」と捉える方が多いですが、小型犬の場合は「お困りの行動」ではなく「愛情表現」とと好意的に受け入れている方がいます。
「飛びつかれた人や犬がどう思うのか」をまずは考え、「好きだから飛びついちゃう」ではなく、愛犬の大きさに関わらず飛びつく行動は相手によって嫌悪感を与えたり危害を与えたりする可能性がある事をが理解いただければと思います。
また、体格や骨格によってはパテラやヘルニアを誘発しやすい行動でもあるため、愛犬の健全性を保つためにも飛びつく行動はおすすめしません。
クン活はさせた方がいいの?
クン活は色んなニオイを嗅いだり鼻を使ったりする事ですが、犬は嗅覚が優れているので、地面に鼻をつけなくても空気中のニオイ(浮遊臭)を嗅ぐ事ができます。
(クン活について) クン活ってなに?愛犬に必要なことなの?
もちろん、地面に鼻をつけたり草むらに入ったりした方がより多くの情報を得る事ができますが、愛犬の望むまま自由にニオイを嗅がせると、感染症、拾い食い、引っ張り、マーキングなどの病気の要因や「お困りの行動」を誘発するリスクがあります。
どうしても嗅がなければいけない理由がある場合は別ですが、それ以外なら嗅ぐ場所や頻度をご家族が制限(管理)する事により、お困りの行動や感染症などの病気を予防できる可能性があります。
絶対「大丈夫」
愛犬の事を深く理解し、適度にしつけやトレーニングわしていると「うちの仔は大丈夫」と自信を持つご家族もいると思います。
自信を持つ事、自信が持てるまでやりきる事はいい事ですが、自信が「過信」にならないように注意が必要です。
些細な事から重大な事まで愛犬は「裏切る」可能性があるからです。
些細な事は目を瞑る事もできると思いますが、重大な事は場合によっては命に関わるものもあります。
誤飲、誤食、拾い食いなどは食べるものや大きさによって命に関わる可能性があり、脱走、お散歩中に首輪胴輪が抜ける、リードが切れるなどは、そのまま逃走して行方不明になってしまったり事故にあったりして命に関わる可能性があります。
「今まで大丈夫だった」経験から、気が緩んだり楽観的に捉えたりする方も少なくないと思います。
年末年始は色んなイベントがあり、イレギュラーな事が起きやすくなるため、「愛犬の命」を守れるように気をつけていただければと思います。
○○できる
「おすわりできます」という方が「愛犬の落ち着きがない」とご相談される事がありますが、「では、落ち着いて欲しい時には愛犬を座らせて下さい」と提案すると「そういう時は座りません」という流れがよくあります。
(しつけについて) 愛犬のしつけ、大事なことってなに?
(愛犬のなぜ?) 愛犬に落ち着きがないのはなぜ?
「できる」状態は各々の認識により異なりますが、スクールでは「どんな時でもできる」事をひとつの目標にしています。
おやつがあればできる場合、おやつより気になる対象ができるとできなくなり、愛犬の気分による場合、「きいて欲しい」時に限っていうことをきいてくれない傾向があると思います。
「限定的」な「できる」は、いざという時は何もできない事が多いので、「できる」状況や条件を増やしてあげる事が愛犬自身や愛犬の命を守る事に繋がると思います。
愛犬と一緒に生活するためには
お困り事の相談の時に、生活環境や接し方のお話をしていると「愛犬が楽しそうにしてるのに?」「○○が大好きだから仕方ない」というお話を耳にする事があります。
愛犬が明るく楽しそうにしている事はいい事で、なるべく愛犬には笑ってリラックスして過ごして欲しいと思う方が多いと思いますが、愛犬“だけ”が楽しくて、一緒に過ごすご家族や周りの人々が「我慢」をしなければいけない状態はよくないと思います。
また、愛犬の行動で許容できる範囲はご家族によって異なりますが、ご近所の方や愛犬に関わる方達の許容範囲もそれぞれ異なります。
例えば、同じ吠え方をしていても、「このくらいなら大丈夫」とご家族が判断しても周りの方は「うるさい」と感じると許容範囲の違いからトラブルになる事があります。
スクールでは、愛犬とご家族が肩身の狭い生活をするのではなく、適切なしつけをして、周りの方々にも可愛がられ愛されるような生活ができる事も目標のひとつにしています。
愛犬“だけ”が変わればいいの?
幼稚園やお預かりトレーニングをして「愛犬にいい変化」が出てくると、「愛犬がよくなったからトレーニングを終わりにします」と言われる事がよくあります。
確かに愛犬にはいい変化が出ていても、それはスクールの環境やトレーナー相手でできているだけなので、ご自宅やその周辺の環境やご家族相手でも「できる」状態になるまでトレーニングは継続される事をおすすめしています。
そのため、「ご家族との練習」や「ご自宅での練習」で愛犬やご家族が安心して生活できるまでフォローをさせていただいています。
愛犬はモノやロボットではないので、「○○ができるようになったのでどうぞ」とお返ししたままという扱いはしません。
いざという時に愛犬を守れるのはトレーナーではなくご家族なので、ご家族が自信を持って「愛犬を守れる」ように、愛犬が「ご家族に身を委ねる」事ができるようになるまでをひとつの区切りとしています。
例えとして適切かはわかりませんが、スマートフォン(スマホ)やパソコンなどを隅々まで使いこなせる方もいれば、最低限だけ使用してたくさんの機能は使いこなせない方や使い方がわからない方もいると思います。
機械の「使い方」をお伝えするように、愛犬のしつけ方、接し方、生活環境をお伝えするのがトレーナーの役割でもあります。
機械が壊れた時、修理や買い替えをしても以前と同じような使用方法をしていると、また同様の故障をしやすいように、愛犬のしつけやトレーニング後も「今まで通り」の生活(トレーニングご依頼前の日常生活)をすると愛犬も「元通り」になりやすい傾向があります。
愛犬に変化を求めるなら、ご家族も同様に変化を受け入れ、今までの日常生活の見直しをお願いします。
さいごに
愛犬が可愛くて大切なのはわかりますが、視野を狭くし過ぎて「思い込み」や「勘違い」をしないように注意喚起を含めた内容を書いてみました。
愛犬がご家族にみせているのは「一面」なので、ご家族が知らない愛犬の一面が他にもあると思います。
「うちの仔は絶対大丈夫」と自信を持つ事は悪い事ではないですが、成長過程による愛犬の変化するや、一緒に暮らすご家族の変化などをきっかけに「いつの間にか」お困り事が出現する可能性はあります。
小さな事の積み重ねで「お困りの行動」に発展したり強化(悪化)したりしやすいため、広い視野で愛犬を理解するきっかけのひとつになると嬉しいです。