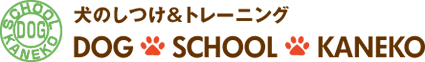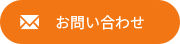こんにちは。ドッグスクールKANEKOです。
愛犬の飼育方法は各ご家庭により様々で、色んな生活環境や生活習慣があると思います。
愛犬との生活は「いつも」の繰り返しのため、日常生活の中で意外と見落としや気付いていない危険が潜んでいる可能性があります。
今回は「身近な危険」として「誤飲」について書いてみようと思います。
はじめに
愛犬はどんな環境で生活をしていますか?
愛犬が「自由に動けるように」「ストレスなく過ごせるように」というご家族の想いからかもしれませんが、知らないうちに愛犬を「危険な環境」で過ごさせているケースもあるかもしれません。
誤飲ってなに?
愛犬が「誤って食べる、飲み込む」お困りの行動のひとつですが、愛犬が食べてはいけない物を口に入れたり飲み込んだりしてしまう危険な行動でもあります。
飲み込む物によっては口から出す(嘔吐)、お尻から出す(うんちや下痢)などで、愛犬が自力で排出できる物もありますが、誤飲した物の大きさや形状によっては排出時に口の中、体内、肛門などを傷つけてしまったり、誤飲物が体内に残ると内臓が損傷したり壊死したりする場合もあり、愛犬の命に関わるケースも少なくないです。
誤飲しやすい環境
愛犬が自由な環境 = ルールのないケージレス(フリー)の環境が誤飲しやすい環境だと思います。
愛犬の自由が強いほど、ご家族が愛犬自身や愛犬の行動を管理しにくい環境にもなり得るからです。
愛犬の生活圏(ご自宅内や敷地内など)を自由に動く愛犬にご家族が付きっきりで監視する事は現実的に難しいため、愛犬が「いつ、どこで、何を」誤飲するかを把握(発見)しにくくなり、誤飲後の対応が遅れてしまう可能性もあります。
例えば、愛犬がご家族の食べ物の盗み食いや食べこぼしを拾い食いなどをしている場合は人の食べ物が入っていた袋(ゴミ)などを食べ物と誤認して誤飲する可能性もあります。
上手く飲み込めずに口の中でクチャクチャしている状態で発見できると口から取り出せますが、排泄物で出たり愛犬の体調(様子)が悪化したりするまで気付かないケースが多いため、誤飲に対する危機感を持ったり、愛犬の行動範囲の物の管理をしたり、愛犬の生活環境の見直しをしたりしていただいた方が安心だと思います。
誤飲しやすいもの
個人的な感覚ですが、靴下、髪ゴム、ボタン電池、食べ物のニオイがする物(フタ、容器、袋)などが多いように思います。
一見、「これは口に入らないだろう」「飲み込めないだろう」と思うものでも誤飲してしまう事があるのが恐ろしいところです。
例えば、焼き鳥やお団子の串などは、食べ物のニオイがするため愛犬が興味を持ちやすいですが、串は尖っているため、口腔内や内臓を損傷しやすいためご家族が食べる際は捨てるまで気をつけて下さい。
ボタン電池は、小型犬でも容易に飲み込めますが、手術が必要になるケースも多いため、普段から自由に動いている愛犬や、愛犬から目を離す事(時間)が多い家庭は要注意です。
誤飲できる大きさや形状
人の感覚だと「これは誤飲できないだろう」と思う大きさや形状の物でも、愛犬が口に入れるだけでなく飲み込んでしまう事があります。
人間の話になりますが、保健師さんに赤ちゃんが飲み込める大きさの目安を教えてもらった事があるため、ひとつの目安や参考にしてみて下さい。
人の赤ちゃんは「トイレットペーパー」や「ラップ」の芯の中を通る物は大体飲み込めるそうです。
なので、ハイハイをしたり、つかまり立ちをしたり、赤ちゃんが自分で動き回れるようになったら、トイレットペーパー(ラップ)の芯を通過する物は危険なので、予め確認してから排除したり、赤ちゃんの手が届かないところで管理したりする事などが必要だと教わりました。
愛犬の大きさや犬種によって差はあると思いますが、小型犬でも「トイレットペーパー(ラップ)の芯」をひとつの目安に愛犬の生活圏で確認をしてみて下さい。
大型犬の場合、軍手やゴム手袋、キーホルダーのマスコットや小さいぬいぐるみなどの大きさの物も丸飲みできる仔がいます。
誤飲は癖になる
誤飲する仔は、誤飲した環境や状況により、癖になる事があります。
一例ですが、ご家族が慌てるのが面白い、ご家族と取り合いになるのが楽しいなど、誤飲時の周りの反応が楽しくてゲーム感覚でわざと誤飲をする仔がいたり、ご家族が必死に誤飲物を取ろうとするのを「これは自分のもの」とムキになって取られないようにするために飲み込んでしまう仔もいたりします。
例えば「取られないように」ムキになる仔の場合、対処法を間違えると取られないように一瞬で飲み込んでしまったり、ご家族に気付かれないように隠れて飲み込んでしまったりするケースもあり、発見が遅れるととても危険です。
そのため、「愛犬の生活環境」の見直しや、愛犬が「飲み込む可能性がある物」の「管理」を徹底していただく事が「愛犬の命を守る」事にも繋がります。
愛犬やご家族が自力で排出できない誤飲の場合、開腹手術が必要なケースがあり、同じような物を繰り返し誤飲してしまう場合、何度も手術が必要なケースもあります。
“極端な話”や“ご自身の愛犬には関係ない”と思われる方も少なくないですが、スクールでは、手術をしたり、発見が遅れて命に関わったり、実際に命を落としてしまったりするリスクを回避するために、生活環境や生活習慣の見直しをすすめる事が多いです。
誤飲をしてしまったら
誤飲をした状況(いつ、どこで、何を誤飲したか)がわかる場合とわからない場合で異なりますが、自己判断で「様子見」はせずに、かかりつけ医に相談したり、早急に病院へ連れて行ったりした方が安心だと思います。
誤飲した状況がわかる場合
愛犬がぐったりしているなどの緊急時は早急に病院へ連れて行った方がいいですが、愛犬が落ち着いている場合でもしばらく様子を見るのではなく、病院で診てもらうか、以下の一例を参考に病院に状況を伝え、診察の必要有無を確認(相談)された方が安心だと思います。
・いつ、何を、どのくらいの量(大きさ)の物を誤飲したのか
・誤飲物の状況(全て出せた、一部出せた、全て出ていない など)
・自力で排出できた場合はその時間や量(全てなのか一部なのか)
・誤飲時からの愛犬の様子 など
誤飲は時間の経過で状態が急激に悪化したり、治療の選択肢が少なくなったりする可能性もあるため、個人的には病院で「みえない部分」を確認してもらった方が安心だと思います。
誤飲した状況がわからない場合
基本的には何をどのくらい誤飲しているのかわからないため、早急に病院で診てもらった方がいいと思いますが、誤飲した事がわかる状況や誤飲物の残骸がないと、ご家族は「誤飲した事」に気付いていないケースもあります。
誤飲を排出した物で確認した場合、嘔吐の場合は口の中、うんち(下痢)の場合は口の中と肛門付近を傷がないか確認してみて下さい。
誤飲した物の一部が手元に残っているなら、元々の大きさからどのくらい誤飲をしたのか、どのくらい排出できたのかも確認できると思うため、病院の問診時に伝えて下さい。
愛犬が出したがっているけど出せないなどの場合は早急にかかりつけ医に診てもらい、緊急時はかかりつけ医以外でも診てもらった方が安心だと思います。
自力で排出できず、体調が悪い、様子が普段と違う場合は、誤飲した事を知らない(気付いていない)ご家族からすると「なんかおかしい」程度だと思いますが、誤飲した物によっては命のカウントダウンが始まっている可能性があるため、誤飲と気付けなくても愛犬の様子や反応が気になる場合は、早めにかかりつけ医に相談し、適切な診察、検査、治療をしてもらった方がいいと思います。
愛犬に誤飲をさせないためには
愛犬が「誤飲できない」ように「愛犬の生活環境」を整え、ご家族が「愛犬を管理できる」ようにしてみて下さい。
そのためには「ご家族が愛犬から目を離す時」は、愛犬は「ハウスに入る」習慣をつける事が1番安全安心だと思います。
(ハウスについて) 愛犬はなんのためにハウスするの?
あとは、万が一誤飲してしまった時に迅速に摘出できるように「出せ」「ちょうだい」「アウト」など「口から出す」練習や、愛犬のどこをどんな触り方をしても嫌がらないように「色んな触り方」の練習を日頃からしてみて下さい。
誤飲に対する意識
犬に関わる仕事をしている方は知識としては誤飲の恐ろしさをご存知の方が多いと思いますが、自分を含めトレーナー(訓練士)の知り合いは誤飲に危機感を持っている方が多く、なにも制限なく自由な環境での管理やお留守番はさせられないため、ハウスを活用している方が多いです。
留守番時や、ちょっと目を離した時に誤飲をする仔も少なくないため、ご家族が帰宅したり気付いた時には愛犬の様子が変だったり、最悪命が失われていたりする可能性もあるからです。
見守りカメラで留守番時の愛犬の様子を確認されている方も増えているようですが、誤飲に関しては「カメラで見守っているから安心」ではないです。
また「今まで平気だったから大丈夫」ではなく、まずは生活環境や生活習慣のチェックをしてみて下さい。
さいごに
誤飲は「あっという間に命が失われてしまう」可能性があるのに、各ご家庭での「意識の差」が大きい事のひとつだと思います。
誤飲で1度でも愛犬が手術をしたご家族は、2回目がないように気をつける方もいますが、何度も繰り返し誤飲をさせてしまう方もいます。
誤飲をして、愛犬の命に危機があったご家族は特に後悔をしている方が多いですが、今後「誤飲させないためにはどうすればいいのか」がわからない方も多いようです。
誤飲をしたから誤飲する事「だけ」に問題があるのではなく、生活環境、生活習慣、ご家族との関係性、愛犬への接し方など「誤飲をした背景( =日常生活)」からの見直しが必要なケースが多いです。
日常生活や愛犬の行動など、気になる事があればお気軽にお問い合わせ下さい。